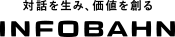コンテンツマーケティングを実践する意義

最近、大企業のオウンドメディア案件を担当する中で痛感していることがある。今さらかもしれないが、「代理店にできないことをやらないと(できないと)意味がない」ということだ。
クライアントの担当者が口にするのは、軒並みこうである。
事業が異なっていても、担当の部署が違っても、口をそろえて指摘する問題点は同一である。
また、クライアント社内でも抱える問題は大きい。
これらを解決しうるのがインフォバーンでなければ意味がない。
“社内を横断する交通整理役”は、企業が大規模になればなるほど、その存在を社内に見出すのはとても難しい。代理店となると、その交通整理役が複数名にわたることで、伝言ゲーム形式となり、最終的には情報伝達のタイムロスにつながることも多い。インフォバーンであればPMあるいはCCOがこの役割を買って出て、社内外を交通整理し、誰よりもこのメディアに対して深いコミットをしていくべきである。結果的に“切っても切れない”関係となり、クライアントとの付き合いを長くすることができるのも、案外こういった側面が強いのではないかと感じる。
「資産」という意味では、CCOはクライアント以上の企業理解が必要になる。部署やブランドを超えた理解を深め、担当者さえも気づかなかった価値を見出し、翻訳してオーディエンスに的確に届ける。これ以上にない企業理解といえる。CCOは、誰よりもクライアントの企業や製品に詳しくなる必要がある。特性や差別的価値を知り、ときには利用者の声を聞くこともある。しかし、過度な入れ込みは禁物だ。“押し売り”にならないコンテンツを届けるためには、フラットな視点が不可欠だからだ。
目標とコンテンツの評価・測定について
Analytics関連の講義やセミナーを受けるたびに、測定値の指標として必ず話題にあがるのは、ECの売上やキャンペーンの参加者数である。どうすると「カートへ入れる」ボタンへのCVが上がるのか。どちらのバナークリエイティブのほうがクリックされやすいのか。サイトや施策の特性に関わらず、数値と結びついているのはいつもUIやUXであり、コンテンツマーケティングの効果測定に関して触れられているのは一切耳にしたことがなかった。コンテンツマーケティングが体系化されてから日が浅いということもあるだろうが、私はそれが非常に不満であった。
本書では、目標ピラミッドを軸に、チーム内での各担当者が見るべき指標が明らかにされている点が非常に新しいと感じた。CCOおよび編集者もAnalyticsの知識をつけ、日々数値と向かい合うことは必須だ。しかし、PMやテクニカルディレクターと同じ数値を追っていたのでは意味がない。コンテンツを制作しているからには、コンテンツに反映されるべき指標を追う必要がある。オーディエンスの共感軸を見出し、より拡大していくのがコンテンツの制作者だからだ。
より細分化された視点で考えると、コンテンツのカテゴリーだけでなく、タイトルのライティング、本文の構成とライティング、本文のボリューム、ネタの深度、ビジュアル、あるいはリリースするタイミング等、見ていくべきポイントはたくさんある。これから運用していくオウンドメディア案件においては、より具体的な法則性を見出していきたいと考えている。
おろそかにしがちなチャネル戦略
オウンドメディアの制作を進めるにあたり、意外とおろそかにしがちであり、かつ定めたストーリーの中に取り込むのが難しいのが、各チャネルであると感じている。
提案および制作の初期段階においては、全体のコミュニケーション戦略の中で描かれる各チャネル。コーポレートサイト、ブランドサイト、Twitterの企業アカウント、Facebookページ……etc。トラフィックの流入元となる、貴重なチャネルである。ローンチ当初は認知度ゼロのオウンドメディアにとっては、はじめは頼らざるを得ない大切な存在である。
しかし主軸のオウンドメディアに関する議論が活発する中で、いつしか忘れ去られ、思い出されるのはテストアップの最終確認も済ませたローンチ直前、というケースがある。実にもったいない話である。
本来であれば本書にあるように、役割や論調、オーディエンスに期待する行動などは各チャネルで異なるはずであり、適切に連携することで、その力を何倍にも増大させることができるものである。各記事・投稿内容はもちろん、トーン&マナーや公開のタイミングなども、すべて一貫してコントロールできるのが理想である。しかし、組織体制や制作フローの問題により、それがままならないことも多い。クライアントによっては、既存チャネルはルーティーン作業の一環でもあるため、議論自体が後回しになってしまったりもする。
チャネルによってはアンコントローラブルな場合においても、各チャネルがもたらす重要性を事前にクライアントに伝えるだけで、想定のコミュニケーション戦略に少しでも近づけることは可能なのではないかと考える。
本書を実践でどう活かしていくのか
オウンドメディアという名のとおり、メディアの成り立ちやスタイルにはown=それぞれ独自のもの、があると思う。当たり前ながら、クライアント社内の体制をはじめ、予算や規模感、課題や目的も千差万別だろう。たとえば、一般のWebメディアの収益は大きくわけて、①広告販売(例:GIZMODO)、②商品販売(例:OZmall)、③コンテンツ販売(例:食べログ)のいずれかによると思うが、オウンドメディアとなると、①~③のどのケースにも当てはまらないもののほうがむしろ多い。それだけ目的、目標設定が多岐にわたるといえるだろう。
そのように考えると、本書のマーケティング戦略のプロセスすべてがあらゆるオウンドメディアにおいて当てはまるかというと、一概には言い切れないと思う。
自分が担当しているK社のオウンドメディア案件であれば、あえてペルソナ設定は行わなかった。商材がオールターゲットの家庭用品ということで、絞り込むことは危険と判断したためだ。そのかわり、これまでリーチしきれていないと想定される、男性、若い女性、シニア層などを積極的に取り込めるよう、それらのターゲットを意識したコンテンツテーマを取り入れた。
オウンドメディアの形によっては各ステップを、飛ばす、簡略化する、あるいはあとから議論する、などの形も想定しうるだろう。しかし、これらの場合もマーケティング戦略のプロセスを「知っていてあえて飛ばす」のと「知らずに、議論の余地も残さずに進める」のとでは、大きな違いを生む。それは、社内上層部や他部署の説得しかり、運用がスタートしてからの施策の拡大しかり、知らずに進めることでのコンテンツや施策の“ブレ”が生じる可能性がある。当たり前ながら、ブレたコンテンツでは、狙った相手に的確に届けることは難しい。
そのような取り返しのつかないことにならないようにするためにも、チーム内で各ステップの必要性の有無を議論しておくことは重要だろう。そして、方向性や意識を統一しておく必要がある。結果的に「飛ばす」「簡略化する」「あとから議論する」という選択肢を選んだとしても、問題ないと考える。