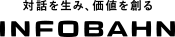中心よりも“周辺”が面白い! 来たる移住イノベーターの時代【鈴木円香対談3/3】

2023年2月14日に、一般社団法人みつめる旅・代表理事の鈴木円香さんをお招きして、弊社代表取締役会長(CVO)・小林弘人との対談を実施いたしました。
コロナ禍以降、すっかり社会に浸透した「リモートワーク」。その定着の影響もあり、東京一極集中の問題が長らく叫ばれていた日本でも、首都圏から地方へと移住する人が増加するなど、変化の兆しが見えています。
そんな今、「東京よりも地方のほうが面白い」と語る2人。一方では、「地方衰退」が現実の危機として迫っているなかで、なぜ鈴木さんは東京という「中心」ではなく、五島という「周辺」に魅力を感じるのか。なぜ小林は移住イノベーターの存在に注目するのか。
地方のリアルを知る2人による、地方とイノベーションに関する対談の模様をお届けします(第3回/全3回、第1回はこちら、第2回はこちら)。

※読みやすさを考慮し、発言の内容を編集しております。
********************
社会課題のリアルを知る「本気の社会科見学」
小林弘人(以下、小林):鈴木さんにお持ちいただいたものの中に、すごくお洒落なノートがありますね。これはワークショップをやられた際のノベルティですね。
鈴木円香(以下、鈴木):私たち「一般社団法人みつめる旅」の代表理事の一人に、大手企業のR社に勤める日高誠人という者がいるんですけど、R社は起業家を輩出する企業として知られていて、社員が40歳までにポンポン独立していくのが、けっこう普通のキャリアパスなんです。でも、日高は、40歳を超えてもそのまま社員として働いていて、すごくキャリアに悩んでいたらしいんですね。
そんなときに、五島で1週間の「リモートワーク実証実験」ツアー(※こちらの記事を参照)の運営に参加したら、そこで人生観がすごく変わって「置かれた場所で咲きなさい」じゃないですけど、何か「ここで頑張ろう」って思えたそうです。
それで、「視野が広がったこの体験を、自分みたいにキャリアで悩んでいる東京のビジネスパーソンに広めたい」ということで、彼が研修商品をつくったんですよ。「みつめる旅humanity」という4泊5日のプログラムで、山口周さん(※1)にご同行いただきながら、潜伏キリシタンの遺跡を中心に五島のいろんな場所をめぐって、ダイアローグして、というツアーをしました。このノートは、そのときにおまけとしてみなさんにお渡ししていたノートですね。
小林:ノートの前半冒頭に山口さんの文章が掲載されていますね。紙質もすごく素敵で、心くすぐられるようなポイントになっていて、鈴木さんという編集者のこだわりがないと、なかなかこういうノベルティは出てこないなと思いますよ。
それ以外にも、最近では「本気の社会科見学」というプログラムを組まれたと聞きました。
鈴木:ワークケーションの企画ですね。「五島ワーケーション・チャレンジ(GWC)」というのを2019年からずっとやっているんですけど、その最新版、2022年度冬バージョンです。「2040年の日本を体感しに行こう――人口減少の中に希望を見出す本気の社会科見学」と題してやりました。「五島列島をタイム・ワークスタディする」というコンセプトで、五島列島ってご存じのように、国境離島で人口減少がすごく激しいんですね。高齢化率も40%を超えていて、本当に将来、日本全国で起こるであろういろんな課題がもうすでにいろいろと起きているんです。
水インフラとか、森林保全の問題とか、エネルギーの問題、交通の問題……いろんな課題をそれぞれワンデイ・ワンテーマで見学するプログラムです。そこには、大企業の経営企画部の方とか、新規事業部の方とかに来ていただけました。ゲストとしては、ベストセラーの『未来の年表』(講談社現代新書)を書かれた河合雅史さん(※2)に来ていただいて、一緒に回りました。

小林:ご参加された方々の反響はいかがでしたか?
鈴木:今ちょうどみなさんにインタビューしているところなんですけど、「期待を上回って良かった」という声をいただいています。「今まで自分たちは新規事業としていろんな事業を考えてきたけど、現実をちゃんと見てなかったことに気づきました」「こういうことが日本の地方では起きてるんだと、初めて知りました」というような、企画者としては嬉しい反応をいただいていますね。「もっと部下を送りたい」っておっしゃられる方もいました。
小林:そこには、課題がある場所にフィールドワークとして見に行くだけではなくて、行った方々同士のコミュニケーションもしていることもあるんじゃないですかね。
鈴木:そうですね。だいたい毎日、全国の統計的な情報のインプットとかの座学をしてから、フィールドワークに出かけて、帰ってきてからも2時間、参加者同士でダイアローグをするんですね。見てどうだったとか、何を考えたかを話し合う。そこはやっぱり参加者の方同士の交流会みたいな雰囲気になります。
小林:なるほど。そのファシリテーションも鈴木さんがやられているんですか?
鈴木:あ、そうですね。私と、代表理事の一人である遠藤貴惠と、2人でやっていますね。
小林:やっぱり何でも自分自身でやられてますね。
鈴木:やっているというより、やらざるをえないんですよね(笑)。
小林:僕らも日本国内やベルリンで、そうした視察プログラムをやっているので、非常によくわかります。やっぱり実際に現地に行かないと、わからないことは多いですよね。
鈴木:わからないですね、本当に。
小林:そういう意味では逆に、課題山積な場所というのは、いちばんエッジな場所でもあるんですよね。課題先進村というか。一番先に訪れちゃうからこそ、ソリューションをすぐに生み出さないといけないという「待ったなし」感がある。
そのうえで、そこには他の場所でも活用できるアイデアがあると思うんですよね。だから、本当に逆に最先端という気がしますね。
――――――――――
※1 山口周
1970年生まれの著作家、独立研究者。電通、ボストン コンサルティング グループなどを経て独立。『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』など著書多数。
※2 河合雅司
1963年生まれのジャーナリスト。産経新聞社入社後、論説委員などを経て、人口減少対策総合研究所理事長に就任。『未来の年表』など著書多数。
これから「地方イノベーター」の時代が来る
小林:ここでちょっと一回五島を離れて、日本の近未来のお話をしたいと思います。五島での経験を通じてお感じになってきたことを踏まえて、「こうなったらいいな」「こうなるんじゃないか」という編集者の予感的なことを。野性の勘でもかまいませんし、何か論理的なデータベースを基に気づかれたことでもかまいませんし、その辺をおうかがいしたいと思います。
鈴木:そうですね。私はこれまでの人生で、自分がまったくデータベース的な人間じゃないことをよくわかっているので、直感になりますけど、「周辺」ほど面白いだろうなっていうのは思います。マージナルなところ、中心から離れたところこそ、面白い。
新しいことを始める余地がものすごく広いんです。初期投資も少なくて済むし、ビジネスが絡んでいないぶん、純粋な情熱を集めやすいというか、良い仲間を集めやすい。
小林:一時期、コワーキングスペースとかに起業したい人たち同士が集まって関わっているうちに、「じゃあ一緒に何かやろうか」と動き出していたような。その情熱に似ていることが、地方で起きているというのは感じますね。
鈴木:そもそも課題として人がいないじゃないですか。だからこそ温かくて、「来てくれた人はみんなウェルカム」っていう感じがするんですよね。それはもう外国人であろうと、年齢がいくつであろうと関係ない。
「来てくれた人で力を合わせて何かやろう」っていう熱は、人口が減っている周辺地域にこそ、それが広がる余地があって面白いんじゃないかなと思っています。東京で仕事していると、「この人はどんなスキルを持ってるんだ?」とか、「性格的にどうだっけ?」とか、選り好みするじゃないですか。そのぶん、今いる人で頑張ろうとはならない。そういう意味では、周辺がとても面白いなって思いますね。逆に多様性がある。
小林:確かに、ヘタにタレントをリストにズラリと並べられちゃうと、「この人は高そうだからやめようか」とか、そういう変なフィルタリングがかかったりしますよね。10年以上前から地方に移住している僕の知り合いがいるんですけど、彼は先見の明がすごくあって、「移住イノベーターが、これからの時代は来る」ってずっと言っていたんです。
鈴木:すごいですね。
小林:「東京はもうレッドオーシャンだ」と。「東京でやるよりも、そのアイデアとスキルがあるんだったら、地方でやったほうがブルーオーシャンなのでうまくいくよ」って言っていて。
実際にうまくいっている人たちが、僕の周りにはいっぱいいるんですよ。東京の渋谷とか原宿とかで同じことをやっても、大資本の企業もあるし、巨大チェーンもあるので、負けてしまうかもしれないところで、そのクオリティーを地方に持って行ってやったことで、県外からもお客さんが来くるくらい繁盛している飲食店もありますよね。そういう移住イノベーターたちが、日本の新しい未来をつくっていくんじゃないかなっていう予感はしますね。
鈴木:本当にそうだと思います。あと、その周辺部分が面白いことのなかには、海外とつながる余地が大きいということもあります。日本国外から多様な人が来てくれる可能性がある。
小林:僕は「超関係人口づくり」って言葉を使うんです。「超」を付けているのは、住んでもいないし、1年に1回来れるかどうかという関わりでも、「そこが好きだ」という想いがある海外の人は多いんですよ。バーチャルなコミュニティーをつくったり、常に届くように情報を発信していったり、そういう人たちとどうつながるか。
鈴木さんは「バーニングマン(※3)」というイベントを、ご存知ですか?
鈴木:はい、存じ上げてます。
小林:「超関係人口づくり」の最たる例が、「バーニングマン」だと思うんですよ。あそこは誰もいない土地なんですけど、そのイベントが開催されるときだけ世界中から人が集まって、人口5万人くらいになるんですよね。プライベートジェットに乗ってきたり、キャンピングカーに乗ってきたり、いろんな人が集まる。そういう「超関係人口づくり」を視野に入れて、国際的にも今後、取り組む自治体が出てくるんじゃないかなという気がします。
鈴木:そうですよね。私も五島で「バーニングマン」をやりたいんですよね(笑)。
そういう尖ったコンセプトを、尖った場所でやると、ものすごいパッションのある人が集まって来るので。外国人も含めてそういう人が、またさらに強い関係人口になってくるんだろうなと思います。
日本国内でも海外でもいいんですけど、とにかく「五島に変態を集める」っていうのは、我々の一番のミッションですね。五島に才能豊かな変態を集め続ける。今やっていることはすべて、そのための手段でしかないんですよね。
小林:僕はここのところコロナ禍で海外に行けなかったんですが、日本をあちこち見てきて、いろんな人たちとお会いして、お話をおうかがってくるなかで、東京に戻ってきたときに、むしろ東京のほうが退屈に感じられるときがあるんですよ。
鈴木:わかります(笑)。
小林:もちろん東京で頑張られている方たちもいらっしゃるし、東京を否定しているわけではないんですけど、東京で面白いことをされている方たちも、東京の中のエッジでやってるんですよね。商業施設がたくさん集中してるような場所じゃなくて、「シャッター商店街になっちゃった、どうしよう」というようなところで活躍されていたりする。
これは逆転現象で、僕が若いころの80年代だと、絶対に東京が面白かったんです。世界中から東京に集まってきていましたから。それが今では、地方のほうが面白いと思いますね。
鈴木:そうですね。私なんて東京と五島の両方を行き来しながら仕事しているじゃないですか。仕事とはいえ、五島での仕事は東京での仕事とまったく違う。いわゆるビジネスとは無関係の世界で副業しながら、本業ではバリバリのビジネスの世界に身を置いてるので、私にとってここを行き来するのは、とっても発見が多いですね。
――――――――――
※3 バーニングマン
アメリカ・ネバダ州のブラックロック砂漠で毎年開催されるイベント。世界中から8万人ほど集まり、参加者主導でゼロから町が築かれる世界最大級の奇祭。
「教育環境」が地方創生のカギを握る
小林:そうしたアドレス・ホッピングをできるようになるためにも、ずっと持論として言っているのが、行政区またいでも子どもの学業の単位が引き継がれるようにすることですね。たとえば、普段通っている小学校の授業を途中で2ヶ月くらい休んで、別の地域の別の小学校に行こうとしても、引き継げないんですよね。
この実現はなかなか難しいらしくて、徳島県のように一部では実施されているんですけど、それも学校長の一存として進めているようで。ここをクリアできれば、かなり自由な生活ができるようになるファミリーは多いと思うんですが……。
鈴木:そう思います。私も子どもが保育園に通っていたときは、かなり機動性高く動けたんですけど、小学校に上がった瞬間に動けなくなっちゃっいましたからね。単位交換ができるようになると良いですよね。
小林:子どものためにも、良い経験、良い勉強、良い教育になるんじゃないかと思うんですけどね。
鈴木:私たちのワーケーション・プログラムでも、お子様連れの方へのサポートは充実させています。というのも、私自身も子どもがいたので、必ずお子様サポートがないとワーケーションには全然行けないということが、わかっていたので。
今はコロナ禍でできてないんですけど、その前は小学校の一時体験入学っていうのを組み込んでいたんですよ。お子様が、普段とはまったく違う環境、初めてのクラスの中にいきなり一人で放り込まれるんです。そこで、みんなから歓迎されるので、「もう帰りたくない」っていうくらい毎回良い反応が起きてました。
それでもやっぱりお子様を連れてくる親御さんは、「欠席扱いになっちゃうけど、豊かな体験をさせたいから、1週間インフルエンザにかかったと思って連れて行きます」っていう意思決定をされていたので、そこが出席扱いになったらどれだけ良いだろうかと感じますね。
小林:文科省も、STEM教育だ何だと言っているんだったら、リモート授業でもいいじゃないか、受けさせてあげなよって思いますね。僕の小学生の子どもはNotepad++(※4)を使っているんですけれど、自分では使っても学校ではほとんど何も使ってくれていない。もちろん小学校の先生方も、いろいろな業務で忙しすぎて新しいことを始めるのは大変だとは思うんですけど、休んだ子たちに対してリモート授業を受けさせてあげるくらいはしてもいいんじゃないかなとは思いますね。
鈴木:本当にそうなんですね。今のツールを使ったら、全然技術的なハードルは高くないと思うんですけど、なかなかそこを変えるハードルが高いんだなって思います。この3~4年、私たちも全然そういうところは前に進められてないんです。
小林:仕事で関係を持っている長野県白馬村なんかは、子どもを預かってくれる体験イベントも企画していますね。親とは別に、子どもが昆虫を見に行くデイキャンプのようなイベントを提供しています。親がワークショップに参加されている間に、お子さんにも教育的な体験ができるように設計している。
そうした何か機能や仕組みができるように整えれば、かなり参加者にとっても間口も広がってくるんじゃないかと思います。
鈴木:それは絶対にそうです。私たちもキャンプをやっています。「本気の社会科見学(※前回記事を参照)」でも、月曜日から金曜日までの5日間、大人たちが社会科見学に行く間に、子どもたちは0⇒1の発想力を鍛える「秘密基地キャンプ」というのに参加できるようにしていたんです。福岡に「センス・オブ・ネイチャー(※5)」という、アメリカで野外教育の資格を取られている集団が実施しているキャンプがあるんですけど、彼らに手伝っていただいて、自分たちで月曜日からベースキャンプをつくって、木曜日と金曜日にキャンプをするという企画を実行しました。
やっぱりセットですよね。親子両方に充実したコンテンツがないと、なかなか来てもらえないのかなという実感があります。
小林:イベントを企画する側の僕ですら、一定期間拘束されるワークショップやワーケーションには、家族で行けないとつらいっていうのがありますからね。育児もあるので、単身で行くわけにもいきませんから。
――――――――――
※4 Notepad++
Windowsで利用できるフリーのテキストエディター。
※5 センス・オブ・ネイチャー
アメリカ・コロラド州の「サンボーン・ウェスタン・キャンプス」をモデルに、九州各地の自然を舞台として、野外教育のプロが企画・指導する子どもキャンプ。