
2023年9月14日に、Henge Inc.代表の廣田周作さんをお招きし、『Next EditorShip:編集者がビジネスリーダーになる時代』と題して、弊社代表取締役会長(CVO)・小林弘人との対談イベントを実施いたしました。
新聞や雑誌、書籍といった伝統的な紙のメディアが経営的な苦境に立たされる一方で、昨今「編集者」という存在が活躍する舞台は広がりを見せています。そんななか、本イベントでは、従来のメディアの枠にとどまらない、ビジネスや社会活動においても発揮すべき「EditorShip」について議論しました。この記事では、本イベント前半の模様をお届けします(第1回/全3回、#2、#3)。
イノベーションリサーチの背後にある「編集」視点
小林:インフォバーン代表取締役の小林弘人と申します。もともと私のバックグラウンドは編集者でして、1994年に『WIRED JAPAN』という雑誌を創刊して以降、『サイゾー』を創刊したり、「ギズモード・ジャパン」というオンラインメディアを立ち上げたりと、数え切れないほどいろいろなメディアに関わってきました。
今日は「Next EditorShip」をテーマに、お話をさせていただきます。ゲストには、廣田周作さんをお招きしています。
廣田:廣田周作と申します。最初にエクスキューズを入れますと、僕は「編集者」として仕事をしたことはないんです。編集者になりたくて就活で出版社を受けたけど、全部落ちてしまったという者でして。キャリアとしては、広告代理店の電通で10年ほどプランナーやリサーチャーをしていました。それから2018年に独立して「Henge」という会社を立ち上げ、今は主に3つの事業を展開しています。
1つ目が、イノベーションリサーチ。世界中のプロダクトやサービスの最新事例をひたすら集めてきて、それを分析しながら、企業の研究開発やマーケティング戦略に活きる情報を提供する仕事をしています。2つ目が、ブランド開発です。イノベーションリサーチで得た知見を使いながら、クライアント企業の持っている技術をどうやってプロダクトやサービスにつなげるか、ブランディング視点でサポートしています。それから3つ目が、付き合いのあるスタートアップ企業にエンジェル投資をしながら、どういうビジョン・ミッションにしていくかを考えるお手伝いをさせていただいています。
特に「編集」というテーマに関わるのは、イノベーションリサーチだと思いますが、これはイギリスにある「STYLUS」という広義のメディアカンパニーと協業して行っています。最新のプロダクトやサービスに対して、その消費者の価値観がどう変わっているか。あるいはeコマースだったり、PRの仕方だったり、常々新しい手法が出てくるなかで、どんな新しい売り方があるのか。STYLUS社は、そういった情報を収集して、編集して、企業の戦略に活かすような記事をつくっている会社です。
私はそこと提携して、世界で流行ってるもの、新しいものを理解し、その背景にあるコンテクストやインサイトに基づいて、クライアント企業を支援する活動を行っております。
小林:STYLUS社は、もともとは出版社ですか?
廣田:いえ、もともとはカラー・マテリアルのリサーチ会社として始まった会社です。メディア化していくなかで、ハーストの資本が少し入っていますね。
小林:ハーストというと、有名なアメリカの出版社ですよね。
廣田:そうです。日本では『婦人画報』などを刊行しているハースト婦人画報社の親会社ですね。マーケティング・レポートというのは正直、味気ないものも多いんですが、STYLUS社の記事では、雑誌のようなクオリティでビジュアルをつくり込んだり、コンテクストを整理したうえでプロダクトを紹介したり、きちんと編集視点を入れて制作しています。
「Future Insight」という言い方をしているのですが、最終的には単なる情報ではなく、企業がどういった研究開発していけばいいかのヒントになる未来への洞察を提供している感じですね。
小林:本当に雑誌のようにきちんと編集されているので、いわゆるホワイトペーパーの無味乾燥さがなくて、どんどん読みたくなりますよね。
廣田:まさに読み物としてつくられています。ビジネスモデルとしても、多くのウェブマガジンは、広告モデルを採用していますけど、これは会員制なんです。サブスクリプション・サービスとして会員企業に情報提供しながら、僕がその企業におうかがいして、それを一緒に読み解く活動もしています。
小林:なるほど。そういう意味で、出版社でなくても、僕はSTYLUS社さんにも、Hengeさんにも非常に「編集力」というものを感じます。廣田さんも、ご自身は「自分は編集者ではない」とおっしゃいますけど、私は編集者だと思っているんですよ。それにもともとNHKでディレクターをやられていて、メディアの経験もお持ちですよね。
廣田:最初の就職は、NHKに入っていました。1年くらいで辞めてしまいましたけど、ディレクターとして勤務していて、電通に転職してからも番組の企画などを手伝ってはいましたね。NHK Eテレの『ねほりんぱほりん』という番組などでディレクターをしました。
小林:私との接点では、電通と一緒にインフォバーンが立ち上げた「COTAS」というメディアがありまして、そこで廣田さんと知り合いました。今はもう当たり前になっていますけど、「コ・クリエーション(協創)」という考えを啓蒙するために、日本で協創的な取り組みをしている企業や自治体を表彰する、日本の「コ・クリエーション・アウォード」というのを電通さんと一緒に開催しながら、その「COTAS」で協創事例を紹介していたんです。廣田さんは、その編集長でした。
廣田:そうですね。小林さんの次に、僕が担当していました。
小林:だから、実際に編集者なんですよ。
廣田:ありがとうございます。あと、電通にいたときに広報と兼務していた時期がありまして、電通のオウンドメディアである「電通報」をWeb化する際に関わっていましたね。
小林:狭義な意味での「編集者」の仕事は、書籍や雑誌という平面の中で、どんなコンテンツを入れるかを考えて、著者やライターを探して頼んで、それを入稿するというものです。僕はそれを編集エンジニアリングと呼んでいるんですけど、もっと広義な意味になってくると、それだけではなく、プロデュースしたり、人を巻き込んでいったりしなければならない。
もちろん今は、出版社の編集者の方であっても、SNSを活用して発信されたり、プロモーション施策を考えられたりしているんですが、広義の意味で「編集者」をとらえれば、今の時代には出版社の編集者以外にも、かなり多くの人が編集に関わってると見ているんです。
逆に言うと、プロの編集者が持っているスキルというのは、ビジネス・デベロップメントやブランディングなどにも活用できるんじゃないかと。僕が「廣田さんは編集者だ」というふうに感じるのは、そうした考えからです。
廣田:ありがとうございます。本当に恐縮で、僕にとって編集者は憧れがある職種なので、今日はヒヤヒヤしながら話しているところもあります。
編集者的な「言語化」は、新たなモノの見方を生む
小林:それでは本題に入って、最初にズバリ核心を聞きたいんですが、廣田さんは編集のコアにあるスキルはなんだと思いますか。
廣田:一つには、何らかのテーマやコンセプトに対して、しっかりと論点を立てて言語化するところにあると思っています。
小林:それは僕も同意します。たとえば、僕は地方自治体の方と一緒に、地方創生に関するお仕事をする機会があるんですけど、その地方では当たり前だと見なされていることを改めてキーワードとして抜き取って、「これで勝負したほうがいいんじゃないんですか?」と提案すると、「えっ、そうなんですか!?」という反応が返ってくることがよくあります。
そこで僕が何をしているかというと、重要な観点を抽出して、言語化しているわけですね。当然ながらぬるい言語化だと面白くならないので、外部の人も巻き込めるような魅力的な言語化をするために、よく観察してから抽出します。その観察も重要です。
廣田:そうですね。私の仕事で言うと、クライアントにメーカーの研究所が多いんです。どこも一生懸命に技術開発をされているので、「こんな新しい仕様にできました!」といった成果は上がるんですけど、いざ「それはどうサービスにつながるんですか?」とか、「それでどういう付加価値が生まれますか?」ということを聞くと、スペックの話に終始してしまって、なかなか価値の本質の話にいたらないことがあります。
そこで重要なのは、「そもそもこの技術にはどういう価値があるのか?」という視点で、エンジニアの話を、ユーザー側の論理で編集し直すことなんです。そのためには、普段から人の観察もそうですし、技術の使われ方もよく理解しておかないといけないと思っています。
小林:その「ユーザー中心でモノを考える」という点で言うと、「デザインシンキング」もわりと似たようなアプローチじゃないですか。「デザインシンキング」と、僕がよく言う「エディターシップ」や「エディトリアルシンキング」とで、「何が違うんですか?」とよく問われます。廣田さんから見て、両者に何か違いは感じますか。
廣田:これは私独自の考えなので、もしかしたら違和感があるかもしれないですけど、僕がよく言う話で、「順目のアイデアはつまらなくて、否定の否定になっているアイデアが面白い」というものがあります。
つまり、Aという課題に対して、順目に真っすぐ考えていって、正しく解けるソリューションをつくりました、という手順だと、“飛躍”がないんですね。「まあ、そうだよね」と同意は得られても、そこに驚きがない。逆に、こうではないんじゃないか、やっぱりこうかな、と否定の否定をしていくと、一回遠くまで行って帰ってくることになるので、違う形でAという課題をとらえ直すことができて、「実は課題はAではなく、A’として捉えたほうがいいんじゃないか」というような発想の転換が生まれたりします。その「そもそもの課題自体を疑ってみる」という過程が大事なんです。
デザインシンキングの場合は、順目ではなくても、とりあえずあるものをいじってみて、試作していくというふうになるんですけど、編集的な言語化というのは、一回遠くまで飛ばして帰ってきたときに、「違う見え方が見つける」という価値のつくり方かなと思っています。
小林:その過程で斜め上の視点や偶発性が入り込むと。
廣田:はい。デザインシンキングが目指すのが「創出」なら、編集における言語化というのは、「同じものであっても、異なる見立てによって面白くすること」だと思うんです。
たとえば、山梨への旅行となると、富士急ハイランドに行くとか、山中湖に行くとか、そういう楽しみ方が一般的だと思うんですが、それだけじゃない。たとえば、歴史学者の網野善彦さんの本を読むと、「山梨は甲斐の国と言われていたけど、山合いにあるのになぜ甲斐(貝)なのか」という問いが出てきます。そこから、実は山梨には海から来ている古代の遺物がたくさんあるように、川を通じていろいろなところと交易していた場所であるからだと言っています。そうしたとらえ直しをしたうえで行く山梨は、同じ山梨旅行でもまったく別の楽しみ方ができます。
小林:つまり、モノの見方が変わることによって、紡ぎ方が変わるんですね。
廣田:はい。地方創生で言えば、「山梨にイノベーション施設を持ってこよう」みたいな解決策だけではなくて、モノの見方を変えることによって新たな文脈が見つかれば、それを活かす道が見つかるかもしれない。
いきなりつくり始めるよりも、一回スペキュラティブ(思索的)に言語化してみたり、「そもそも山梨はどうやってできたのか?」と考えてみたりする視点が、大事だと思っています。
小林:僕らもよく「そもそも論」で考えます。「そもそも」を突き詰めるなかで、学術的なことを調べたりして、新たな発見が出てくることはありますよね。
都市計画でも、利便性が高いからとナショナル・チェーンのお店をどんどん招致するようなやり方では、そこそこ成功するかもしれないけど、長期的には失敗するのではないか、という話をよく自治体の方とします。どこにでもある店だらけになったら、誰もわざわざ見に来たいと思わないじゃないですか。そこで大事なのは、オリジンが何か。そこならではのカルチャーとか、そもそもその街ってどんな街なのかとか、「そもそも」から掘り起こす作業なんです。
廣田:まさにそうした掘り起こしをするなかで、メーカーであれば技術の使いどころが見えてきたりします。思考をちょっとずらしてみたり、思索の冒険をしたりするときに、言語化ができると、すごくモノの見方が変わるかなとは思います。
「気分リサーチ」で時代のインサイトをとらえる
小林:よく僕は、「気分リサーチ」ということをやっています。社会に流れるムードを探索することは、ググっても出てこないし、AIにもできないので、いまだに僕は重要だと思っています。
2017年の話になってしまうんですが、当時、僕が世界中のいろいろなところを訪れた際に、一緒に回った社員二人と、その体験から得た共通項を言語化してみたんです。
たとえば、当時は「ブルーボトルコーヒー」のようなサードウェーブコーヒーが流行っていて、カリフォルニアのサンフランシスコに行ったときに、その先駆とされるお店に行ったんです。そこでは、庭にあるサボテンを囲んで寝そべりながらコーヒーを飲めて、最高においしかったし、とにかく体験として楽しかったんです。
そこで受けた雰囲気と同じものを、ベルリンでも、アーティストやベンチャー起業家が集うソーホー・ハウスという会員制ホテルで感じたし、ニューヨークのブルックリン近くにあるウィリアムズバーグという街でも感じました。
その体験をもとに部下とディスカッションして、彼女たちが抽出したキーワードが「コンフォート」という言葉です。2017年当時、僕らが良いな、イケてるなと感じた場所は、オフィス街の高層建築ビルにあるようなピッカピカでグロッシーな雰囲気じゃなくて、「なぜかいるだけで落ち着くよね」といったコンフォートな雰囲気だったんです。
もう一つのキーワードは「コネクティビティ」で、ビジネス人脈づくりのために、「ネットワーキングするぜ!」「名刺を配りまくるぜ!」というのとは違う、そこで出会った人と何か関係性が発生するような関係性への志向です。
それから「コンフォート」と「コネクティビティー」を組み合わせて、何か新しいものを考えようと話しました。
ここで出た「ニューカンファレンス」というのは、単なるトレード・ショー、展示会、見本市といったものではなく、参加者同士の交流が生まれるようなカンファレンスですね。
アメリカのオースティンで開かれる「SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)」とか、僕らが公式パートナーを務めているベルリンのテクノロジー・カンファレンス「Tech Open Air(TOA)」とか、昼からビール飲みながら、キーノートをきっちり聞くんじゃなく、ダラダラ聞いたうえで、隣にいる人達と会話が始まるようなカンファレンスが盛り上がっているんです。有名企業のCEOが突然出てきてピッチしたり、イーロン・マスクが来てギターを弾いて歌ったりとかね。そうした新しいカンファレンスが生まれてきている。
それと、レジャーもテーマパークからハロウィーン的な楽しみ方になっている。つまり、お仕着せのものじゃなく、自分たちで楽しむ志向です。実際に今、ハロウィーンの日にコスプレを着て、テーマパークに行く人も増えていますよね。テーマパーク側は開園するだけでも、10月31日にはすごく盛り上がる状況になっている。
そうした形で、あるXというテーマに対して、コンフォートとコネクティビティを組み合わせて考えると、次に何をプロデュースしたらいいか浮かぶのではないかと、ほんの頭の体操としてディスカッションしていました。
廣田:お話からパッと連想したことがありまして、ちょっとニッチな例ですけど、聖書のスタートアップで、「Alabaster」という会社があるんです。
小林:聖書のスタートアップ? どういうことですか?
廣田:わかりやすく乱暴に言えば、ミレニアル世代の若者にとって、これまでの『聖書』は本としてダサいと。そこで、もちろん内容は変えてはいけないのでテキスト自体は一緒なんですけど、雑誌の『KINFOLK』みたいにオシャレな写真を掲載したり、フォントにこだわったりと編集の手を入れて、すごく洗練された聖書をつくったら、ものすごく人気になって、爆発的にヒットしたんです。
まさにとらえ直しによって、手に取る人が増えたという意味で、先ほど整理された視点からもいろいろと見えてくると思います。
小林:勘が鋭い編集者は、そうした気分をうまくとらえてヒットを生み出しますね。特に月刊誌のような雑誌は情報のタイムラインが短いので、トレンドをうまくつかんで「これが読みたかったでしょう?」と提示しないといけないから、気分リサーチが重要なんです。
気分リサーチによって抽出したモノを言語化したうえで、ここでは翻案・接合と書きましたが、それをどうやって活かすかを考える。商品やサービスを売り込むために、こういうふうにしてみようと考えたところに、リーピングポイント、要は跳躍させる点が浮かび上がる。
ここが僕は、「デザインシンキング」との違いだと考えています。「デザインシンキング」は跳躍させちゃいけないんですよね。
僕は「主観を入れろ」と言います。「自分はこれが好きだ」とか、「自分は社会がこうあるべきだと思う」とか、主観からコンセプトも生まれる。それは、「青色が好きだから、ここに青色を入れる」といったことでもかまわないんです。もちろんその主観が、本当にみんなが望ましいと思っている観点かどうかは吟味したほうがいいんですけど、主観を入れることで跳躍が起こるんです。それから具象化していく、巻き込んでいく。そういうようなことを、心がけています。
廣田:ちょっと違う角度からお話しさせていただくと、広告業界で僕がトレーニングを受けたことに、「良いインサイトは、意識と無意識の間ぐらいにある」という考えがあったんですよ。
つまり、みんなが知っている、すでに意識されていることを言っても、「それは当たり前だよ」となって響かない。逆に、無意識すぎることはシュールすぎて「全然、意味がわからん」となる。ちょうどいいインサイトというのは、「言われてみれば、確かにそういうことを思ってたよね」と、共感が生まれるものなんです。要するに、「そうそう、これこれ!」というインサイトは、「ちょうど言語化したかったところなんだよね」と思うようなところにあって、それをどう見つけるかを考えろということです。
小林:まさに月刊誌はそれをしないと売れないですね。ぶっ飛んだ内容でも、面白いと思って買ってくれる人はいるんですけれど、どうしてもニッチになりすぎてしまう。
廣田:この図にある「言語化と具象化」というのでいくと、「求心力と遠心力」みたいな言い方を僕らはしていました。「求心力」は、それ自体が興味を引けそうな問いです。たとえば、今なら「生成AIは仕事をどう変えるか?」というようなものですね。ただ、それは問いとしては引きが強いんですけど、ベタになってしまいがちです。
面白くするためには、「遠心力」も同時にかけないといけなくて、これは意外なネタですね。求心力と同時に遠心力も強ければ強いほど、何か緊張感が生まれて面白くなるというのは、よく話していたことです。
〈後編につづく〉
廣田周作(ひろた・しゅうさく)
Henge Inc.代表取締役
1980年生まれ。NHKでのディレクター、株式会社電通でのマーケティング、新規事業開発・ブランドコンサルティング業務を経て、2018年8月に企業のブランド開発を専門に行うHenge Inc.を設立。英国ロンドンに拠点をもつイノベーション・リサーチ企業Stylus Media Groupのチーフ・コンサルタントと、Vogue Business(コンデナスト・インターナショナル)の日本市場におけるディレクターも兼任する。独自のブランド開発やリサーチの手法をもち、多くの企業のブランド戦略立案やイノベーション・プロジェクトに携わる。
主な著書:
・『SHARED VISION』2013年6月/宣伝会議
・『世界のマーケターは、いま何を考えているのか?』2021年11月/クロスメディア・パブリッシング
小林弘人(こばやし・ひろと)
株式会社インフォバーン代表取締役会長(CVO)
1965年長野県生まれ。1994年に『WIRED(日本版)』を創刊し、編集長を務める。1998年より企業のデジタル・コミュニケーションを支援する会社インフォバーンを起業。「ギズモード・ジャパン」「ビジネス インサイダー ジャパン」など、紙とウェブの両分野で多くの媒体を創刊するとともに、コンテンツ・マーケティング、オウンドメディアの先駆として活動。2012年より日本におけるオープン・イノベーションの啓蒙を行い、現在は企業や自治体のDXやイノベーション推進支援を行う。2016年にはベルリンのテック・カンファレンス「Tech Open Air(TOA)」の日本公式パートナーとなり、企業内起業家をネットワークし、ベルリンの視察プログラムを企画、実施している。
主な著書:
・『新世紀メディア論』2009年4月/バジリコ
・『メディア化する企業はなぜ強いのか?』2011年11月/技術評論社
・『After GAFA 分散化する世界の未来地図』2020年2月/KADOKAWA
※株式会社ライトパブリシティ 社長・杉山恒太郎さんとの対談記事はこちら
※一般社団法人みつめる旅 代表理事・鈴木円香さんとの対談記事はこちら
※株式会社ニュースケイプ 代表・小西圭介さんとの対談記事はこちら
※株式会社グランドレベル 代表・田中元子さんとの対談記事はこちら
※VUILD株式会社 代表・秋吉浩気さんとの対談記事はこちら
お問い合わせ・資料ダウンロード
デザインとコンテンツの力で、
貴社の課題解決
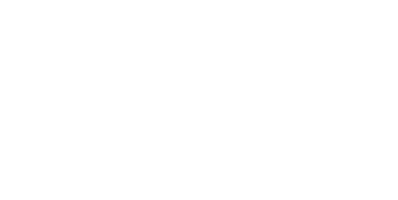 に伴走します
に伴走します
経験豊富な専門チームが、貴社の課題に寄り添い解決まで伴走します。具体的なご相談や詳しい資料をご希望の方はこちらから。






