
人材採用や人材育成、従業員のエンゲージメント向上など、昨今の企業経営において「組織戦略」は欠かせないものとなりました。そのなかで、事業の成長スピードを加速させるためにも、強固で特有性のある「企業カルチャー」を醸成・浸透させる重要性がますます高まっています。
インフォバーンは2024年10月23日に、株式会社ラントリップ・取締役の冨田憲二さんをお招きし、『自律的に社員が働く「組織文化」をデザインするには?』と題したトークイベントを開催しました。同イベントでは、組織づくりにおけるデザイン視点・発想の重要性をお伝えするとともに、一筋縄ではいかない「企業カルチャー」の扱い方について、多角的に掘り下げた議論を展開しました。対談のお相手を務めたのは、インフォバーン副社長・井登友一です。
同イベントの模様を、前編/後編/Q&A編に分けてお届けします(後編記事はこちら/Q&A編記事はこちら)。
組織デザインの基本姿勢は、まず実態を「観察」すること

井登友一(以下、井登):本日は株式会社ラントリップ・取締役の冨田憲二さんにお越しいただきました。
冨田憲二(以下、冨田):冨田憲二と申します。ラントリップは10期目を迎えたスタートアップで、「もっと自由に楽しく走れる世界へ」というミッションステートメントのもと、より楽しいランニングや、ランニングのあるライフスタイルを提案するサービスを提供しています。前職では創業初期のSmartNewsに参画し、社員数が1桁からグローバルで200人強に育つまで、人事の立場で組織を見ていました。
井登:冨田さんは昨年、『企業文化をデザインする』(日本実業出版社)というご著書も刊行されています。実務経験と実績に裏づけられた企業文化への考えが整理され、実用的なレベルにまで落とし込まれている素晴らしい本です。私はこの本を読んでから、ずっと冨田さんとお話ししたいと思っていました。
冨田さんはもともと工学系の学生だったんですよね。エンジニアリングのバックグラウンドを持つ方が、なぜ組織づくりや人材育成、企業文化といった領域に関わるようになったのか。また、なぜそこで「デザイン」というアプローチを大事にされたのか。まず個人的な興味としてうかがえるでしょうか。
冨田:私はもともと車オタクで、高専から、大学、大学院とずっと機械工学、特に自動車の運動制御を学んでいました。ところが、たまたま縁があってIT業界に入り、スマートフォンのアプリケーション開発に携わることになったんです。
「モノづくり」という面では自動車と同じでも、タッチインターフェースに対してどうユーザビリティを高めていくかなど、スマホにおける「デザイン」は単なる見た目ではなく、ユーザーとのインタラクションが勝負所です。いわゆる「人間中心デザイン」をしないと、良いアプリをつくれない。私はディレクターという立場でしたし、今でもデザインの専門家ではありませんが、幸いにも素晴らしいエンジニアとデザイナーに囲まれていたので、自分なりにデザインを勉強し実務で反芻しながら、なんとなく「デザインとはこういうものか」とつかんでいきました。
HR領域に関わるようになったのはSmartNewsに入ってからです。入社当時はエンジニア中心の小さな会社で、私は非エンジニアとして何でも屋的に働いていましたが、組織が大きくなるうちに人事専任者が必要になったので、自分がその役割を担うことにしました。そこで「モノづくり」からは離れましたが、いかに組織をデザインするか、体験をデザインするか、という「デザイン」の観点は人事戦略・施策でも重要だと思っていました。
たとえば、デザインにおける最初のフェーズでは、「観察」が重要ですよね。観察を通して気づきを得たり、対象への解像度を高めたりする。企業カルチャーという曖昧なものに対してこの観察は欠かせないし、特にスタートアップは昨日と今日で形が変わるくらい新陳代謝が激しいので、組織マネジメントではなく「組織デザイン」として捉える必要があるということは、初めのうちから考えていました。
井登:「観察」は非常に重要ですよね。曖昧な対象がどうなっているのか、より良い状態にするにはどうすればよいのか、観察を踏まえて考えることがデザインの基本姿勢です。よく観察し、可視化・構造化することで、共通理解も促進できると思います。
一方で、組織文化は本来的に曖昧で、100%合理的に説明がつくものではないですし、明確にしようとしすぎることでこぼれ落ちるものも出てしまうと思います。その点については、どう考えられてきましたか?
冨田:おっしゃる通り、100%言語化しようとするのは百科事典をつくるようなもので、不可能とは言わないまでも、やる合理性が薄いですよね。だからこそ、多くの企業がカルチャーを明示しようとする際に、真っ先にミッション・ビジョン・バリューを整理するんだと思います。共通言語がないと根本のズレが生じ、社内コミュニケーションがうまくいかなくなるので、上澄みでも言語化するのは基本的に正しいと思います。
ただ、企業カルチャーは本質的に変わっていくもので、ひとたび言語化しても次第に実態から離れていきます。その認識を持たずに運用していけば、実態とズレがあるので無理が生じてくる。企業カルチャーは100社あれば100社で違うので、「ここからここまで」とは言えませんが、いずれ変わるものだという割り切りを持って言語化し、評価制度や採用活動に活かすことが重要ではないでしょうか。「これが正解だ」と思っていると、後で痛い目を見る気がします。
「自社らしさ」への解釈のズレをどう捉えるか?
井登:冨田さんのお話を言い換えると、社員にとって「腑に落ちない状態」になっていく感覚ですね。言葉としては理解できても、「で、それが何なんですか?」と腑に落ちなくなってしまう。
組織研究で有名なカール・ワイクは、組織や人が複雑で曖昧な状況に直面したとき、どう意味付けし行動するかを説明する「センスメイキング」理論というのを提唱しています。ここでの議論で言えば、腑に落ちる状態にいたる合意形成のプロセスをどうデザインするか、という話ですが、そのコツは何かあるでしょうか。
冨田:井登さんの『サービスデザイン思考』というご著書で、「デザインは問題解決とセンスメイキングだ」と書かれているのを読んで、まさにその通りだと思いました。特に企業カルチャーはゼロからつくるものではなく、すでに存在しているものなので、内省しながら理解を深め、解釈する必要がある。つまりは、「センスメイキング」が重要です。
その点で、「うちの会社はこうだよね」という自社のカルチャーをその言動と行動を通じて体現している人が、どこの企業にも必ず1人はいるんですよ。そうしたカルチャーの体現者を見つけ出し、その人を深掘りしてみるのも一つの手だと思います。
もう一つ考慮したいのは、カルチャーデザインにおける「プロアクティブ(事前)」と「リアクティブ(事後)」の分類です。プロアクティブなデザインとは、たとえば能動的にワークショップを実施して、ミッション・ビジョン・バリューを社内で言語化し浸透させていくようなデザインです。それも重要ですが、一方で変化や新たな課題に対応するリアクティブなカルチャーデザインも重要なんです。
たとえば、進化人類学的に人間には、「こいつがボスだ」と認識したら、そのボスを真似る生存戦略があります。誰でも経験があると思いますが、組織には公式・非公式を問わずリーダーシップを取る人が現れて、周りはその人になんとなく合わせ、その人が正しいと考える行動や言動を取るようになります。要するに、意外と人間は自分の意思でアクションはせずに、リアクションで動いている動物なんですよ。
新しく入ってきたボス次第で組織内のリアクションが変わるなら、リアクティブな形のカルチャーも生まれていきます。その側面を考えれば、どれだけプロアクティブに「うちのカルチャーはこうです」と浸透させようとしても、リアクティブな変化もともなう実態からはズレてしまいます。

井登:面白いですね、ただ、人間は十人十色なので、「自社らしさ」の解釈も人によって違いが出てきますよね。たとえば、わかりやすく明示されたミッション・ビジョン・バリューがあっても、それを自分事として考えてもらえばもらうほど、個々人の間で解釈のズレが生じてくると思います。
冨田:そのズレはむしろ大事だと思います。概念上は「自社らしさ」に正解があるとしても、現実には全員が「これだ」と思う解にたどり着けるものではない。だから、企業カルチャーは80点に持っていくだけでも難しいし、100点を目指さなくて良いものだと思います。そもそも個々に解釈の違いが出るくらいの粒度の文章じゃないと、言語化もできないですよね。そこで何より重要なのは、常にその解釈が議論され、話題にされ続けることを通じて、60点、70点と精度を高めていくプロセスをつくり出すことじゃないでしょうか。
「カルチャーフィット」は組織から多様性を奪う?
井登:なるほど。最近は「カルチャーフィットが大事だ」とよく聞かれますよね。先ほど出たカルチャーの体現者というのは、言い換えると「カルチャーフィット」している人で、多くは組織における主流派に位置する人になると思います。
ただ、主流派があるなら、それに対抗する新しい流れ=「カウンターカルチャー」が生まれる余地もあるはずです。このカウンターカルチャーの存在は必ずしも悪ではなく、組織が変化するための新しい流れとして、排斥せずに残したほうが良いケースもあると思います。「カルチャーフィット」という言葉には、全社一丸といった響きがありますが、それではこのカウンターカルチャーはどう扱うべきなのか。
冨田:カウンターカルチャーと似た言葉に「サブカルチャー」がありますよね。組織も一定の規模になれば、会社全体を包括・包摂するメインカルチャーから分離したサブカルチャーが生まれます。
サブカルチャーが生まれる背景には3つのタイプがあると思っていて、一つは単純に分業、職能によるサブカルチャーです。コーポレート部門、営業部門、エンジニア部門でカルチャーが違うのは、それはそれで自然なことです。もう一つは、いわゆる属人的なサブカルチャーで、こちらはだいたい特徴的なチームの長がいて、その人に引っ張られることでそのチームだけ違う空気をまとうようになる。最後が、イデオロギーベースのサブカルチャーで、チームや部門の壁を越えたイデオロギーベースで徒党ができていくものです。
この3分類の中で、カウンターカルチャーになりやすいのは3番目だと思いますが、井登さんがおっしゃる通り、必ずしもそれが悪いわけじゃない。宗教を例に出すと、「チャーチ」の権威に対するカウンターとして、「セクト」というものが出てくる。ユダヤ教からキリスト教が出てきたし、カトリックからプロテスタントが出てきた。一定以上に権威化され暴走を始めると、それに対するカウンターが現れ、ある種のガバナンスとして機能することで、組織全体がより良いものになっていく構造はよく見られるものです。
とはいえ現実には、確実に組織のガンになっているケースもあるでしょうし、それは排除しないといけないでしょうから、実態ベースで個別に見ていくしかない難しい問題ですね。
井登:何を信じるかは人それぞれですし、あるセクトが良いかどうかの判断もかなり際どいものですよね。懸念としては、排他的になればなるほど、組織内のカルチャーの純度は高まりますが、多様性は失われていく。「カルチャーフィット」という言葉が、組織開発やHRの世界でマジョリティーの意見として肯定されている一方で、「ダイバーシティ」や「インクルージョン」も今や当たり前のアティチュードになっています。カルチャーにおける純度と多様性の兼ね合いは、すごく難しい問題です。

冨田:これもやはり、自社のカルチャーをいかに解像度高く理解できるかが鍵だと思います。たとえばラントリップは、ランニング系の事業をやっているので「ランニングが死ぬほど嫌いです!」という人は採用しませんが、だからといって「ランニングが大好き!」という人を採用するわけじゃないんですよ。ランニングはしなくても、「スポーツは好きです」「ランニングの開放感や心身が健康になる感覚はわかります」という人も、採用におけるカルチャーフィットとして許容範囲内です。
そもそもラントリップが目指しているのは、ランニングに対する価値観を広げることです。いまだにランニングの世界では、「オレはこの道を○分で走れた」「この前○○キロ走った」といったタイムや距離のマウント合戦があって、そうした価値観を変えていきたい。ランニング・マーケットを広げていきたいし、ランニング・ライフスタイルを持つことで人生がハッピーになると思ってるからこそ事業を行っています。それなら当然、ラントリップという組織自体が、ランニングの価値観に対してダイバーシティを持っていないといけません。
もちろんダイバーシティとひと口にいっても、そこにはジェンダーなどいろいろな観点があるので、カルチャーフィットを採用基準にするなら、その範囲を各社でもっともっと議論すべきじゃないかと思います。とはいえ、採用に関わる方ならわかると思いますが、100%カルチャーフィットした人材だけを採用するというのも、現実的に不可能なんですよね。その意味では、ジェンダーバランスなどを除けば、意図的に異分子を取り込もうとしたり、入り口で調整したりしなくても、自然と社員の多様性というのは出てくるものだとも思います。
「対話のテーブル」は常に用意しておく
井登:なるほど。カウンターカルチャーへの許容についても、同じようなことが言えそうですね。
冨田:そうですね。カール・ポパーの「寛容のパラドックス」というものがあります。これは「人には寛容であるべき」というテーゼに対して、「それでは不寛容な人に対しても、寛容であるべきか」という問いが引き起こす矛盾で、たとえば差別行為を許容してしまうと、差別者が跋扈する不寛容な社会になってしまいますが、許容しないならテーゼが崩れてしまう。ポパーはその結論として、「寛容が大事だと言っても、不寛容には不寛容で応じなけれならない」としています。
ただ、それも対話が重要であるという話で、何でもかんでも「こいつは不寛容だからキャンセルしよう」ということではなく、「お前は不寛容だよ」と言ったり、「いやいや、俺はこういう意見を持ってるんだ」と言い返したり、互いが対話のテーブルにつけるのであれば、一様にキャンセルする必要はないわけです。不寛容にもレベルがあって、いきなり背後から銃口を突きつけてくるような人に対しては対処するしかないと思いますが、対話が可能なのであれば、まずチャーチ側からそのテーブルを用意することが大事だと思います。
井登:言葉を交わし合い互いを理解するには、まずそれが習慣的に行われる環境がないといけないですよね。これは先ほどの「センスメイキング」につながるのかもしれません。それぞれ少しずつ考え方や表現方法は違うけれど、みんながセンスメイキングしている。そうして極力、腑に落ちる状態が組織の中でふんわりとでもつくられることが、重要かもしれません。
冨田:本当にそうですよね。組織の話は難しく考えがちですが、家族関係でも夫婦関係でも、根本は一緒だと思うんですよ。要するに「対話は足りていますか?」「お互いのことをよくわかっていますか?」という。身近な人とわかり合うことすら難しいことを考えると、やはりコミュニケーションには量が必要なんですよね。質も量から転化します。
生き生きとした良い会社はコミュニケーションが取れています。何よりも経営陣の間で非常にコミュニケーションが取れていて、みんながハッピーな状態にある。経営陣というのは、家族で言ったら両親に当たりますよね。両親の仲が良い家庭は、子どもにとっても良い環境です。人間が集まる組織には、そのシンプルな構造がどこにでもあって、重要なのは血液となるコミュニケーションがうまく循環しているかどうかだと思います。
・後編記事はこちら
・Q&A記事はこちら
*****
【関連記事】
▼人的資本経営で求められる、カルチャーフィットする組織デザインとは?【田中弦×井登友一】
・前編はこちら
・後編はこちら
▼創造性を引き出す「組織文化」をデザインするには?【佐宗邦威×井登友一】
・前編はこちら
・後編はこちら
お問い合わせ・資料ダウンロード
デザインとコンテンツの力で、
貴社の課題解決
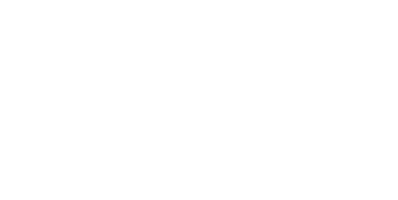 に伴走します
に伴走します
経験豊富な専門チームが、貴社の課題に寄り添い解決まで伴走します。具体的なご相談や詳しい資料をご希望の方はこちらから。






